はじめに

こんにちわ、爪川です
怪我というのは一度発生すると同じ怪我を繰り返しやすくなります
これは脳振盪もそうで、一度脳振盪を受傷するとまた脳振盪になりやすくなります
ただし最近の脳振盪に関する研究では、脳振盪を受傷したアスリートは脳振盪から競技に復帰した後では下半身の怪我の発生リスクが高くなると言われています
そこで今回のブログ記事では、アメリカのプロアメリカンフットボールリーグであるNFLの選手を対象とした、脳振盪とその後の怪我の発生リスクの関係を探った論文を見ていこうと思います
脳振盪と下半身の怪我:NFL選手対象の研究
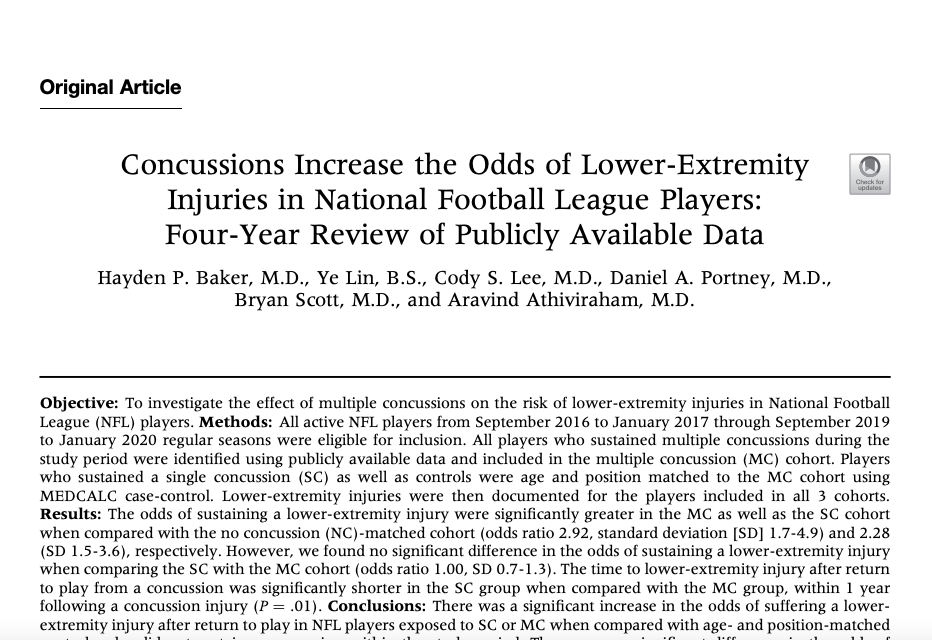
概要
・NFLが公表している怪我の種類や数、4年分(2016-2020)のデータを参照
・脳振盪の発生回数や脳振盪を受傷した選手のその後の下肢の怪我を調査
・脳振盪後の怪我は同シーズン内(プレイオフは含まず)で発生したもののみカウント
・4シーズンで脳振盪を2回以上受傷した選手の数:55名
・4シーズンで脳振盪を1回受傷した選手数:352名
→この352名の中から、年齢やポジションを揃えるように54名の選手のデータを調査
・脳振盪を受傷していない選手との比較のため、年齢やポジションを揃えて脳振盪受傷無しの選手55名を選出
・脳振盪を2回以上受傷した選手(グループ①)
・脳振盪を1回受傷した選手(グループ②)
・脳振盪を受傷しなかったグループ(グループ③)
結果
下肢の怪我の発生数
| グループ① | グループ② | グループ③ | |
| 下肢の怪我発生数 | 86 | 84 | 29 |
・どのグループも怪我の種類としては『捻挫・肉離れ』が最も多く、怪我の発生数の約60%以上を占める
・脳振盪の受傷歴があるグループはそうでないグループに比べて『打撲』の発生率が高い傾向
オッズ比
| 比較対象 | オッズ比 |
| グループ①とグループ③ | 2.92 |
| グループ②とグループ③ | 2.28 |
| グループ①とグループ② | 1.00 |
・グループ①(脳振盪複数回)はグループ③(脳振盪無し)と比較して、下肢の怪我が発生する確率が2.92倍高い
・グループ②(脳振盪1回)はグループ③(脳振盪無し)と比較して、下肢の怪我が発生する確率が2.28倍高い
・グループ①(脳振盪複数回)はグループ②(脳振盪1回)では、下肢の怪我の発生する確率に差はない
最後に

今回のNFLのデータを用いての研究でも、脳振盪後では下肢の怪我の発生率が高くなることが示唆されました
脳振盪を受傷した場合は段階的競技復帰プロトコルに沿ってスポーツに復帰していくことが基本ですが、そのプロトコル通りに競技に復帰したとしても下肢の怪我の発生リスクは高くなることが予想されます
ですので、脳振盪が起きたら(どの怪我でもそうですが)更なる怪我をしないような予防の要素を取り入れたトレーニングの重要性が増してくるかと思います
本日は以上となります
最後までお読みいただきましてありがとうございました


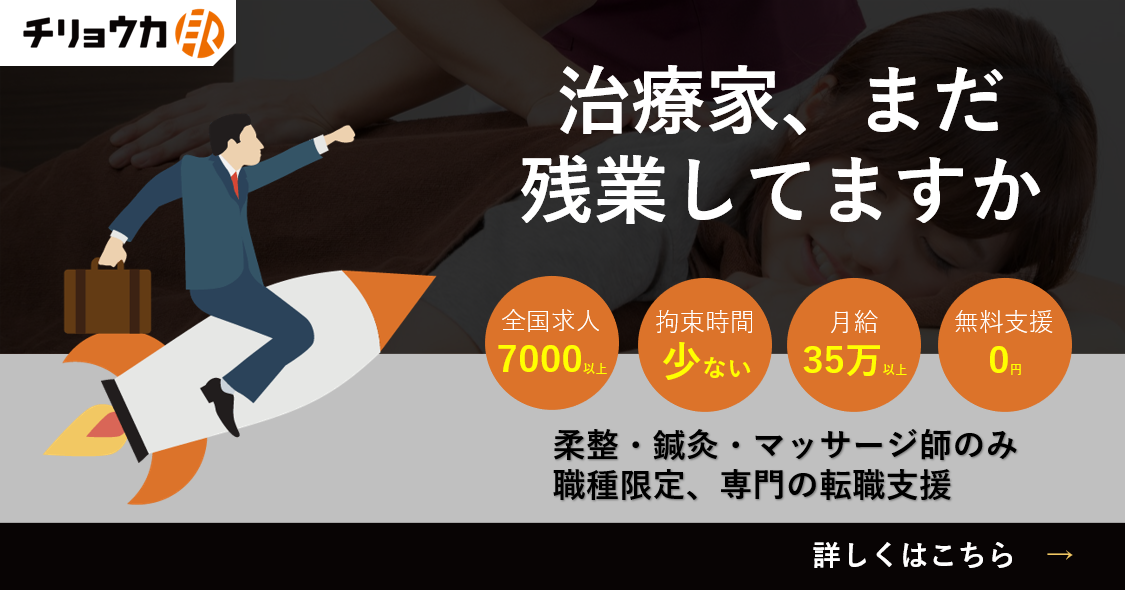




コメント