
こんにちわ、爪川です

前回の記事では脳振盪から競技に復帰した後では下肢を中心として怪我をする確率が高まる可能性について書きました(前回の記事はこちら↓)

そしてその確率が高まる理由の1つとしてNeuromuscular Control(神経筋制御)の機能低下が考えられることも言及しました

ですのでこの記事では脳振盪から競技復帰後のNeuromuscular Controlに関して見ていきます!

まずは脳振盪後のNeuromuscular Controlの低下を示唆した論文を見ていき、その後に実際にNeuromuscular Trainingを競技復帰後に実施した論文を、そして最後にそれらをまとめた考察を書いていきたいと思います
脳振盪から競技復帰後のNeuromuscular Trainingを考える
脳振盪後のNeuromuscular機能の低下

ここでは3つの論文を簡単に見ていきたいと思います

1つ目は脳振盪を受傷したレクレーションレベルのアスリートに対して競技復帰後に片足動作の安定性などをチェックした論文です


この論文では以下の2つの動きをチェックしています
- 30cmのボックスから飛び降りて片足で着地して安定する
- 片足でのスクワット

結果としては①では非利き足では安定するまでの時間が脳振盪から復帰した被験者の方が長く、②では有意な違いはなかったとしています

2つ目の論文は前回のブログ記事でも取り上げたものです

この論文では大学生アメフト選手を対象に、シーズン開始前と開始後での片足ドロップジャンプの状態をチェックしています


この論文でも25cm程のボックスから飛び降りた時の下肢の動きや関節にかかる力などを見ています

結果としてはシーズン中に脳振盪を受傷した選手はボックスから飛び降りた際に股関節のstiffnessは上昇し、膝関節と下肢全体のstiffnessは減少したと報告しています

3つ目の論文は脳振盪を受傷したわけではないですが、女子ラグビー選手のシーズン前後でのバランス機能をチェックしたものです
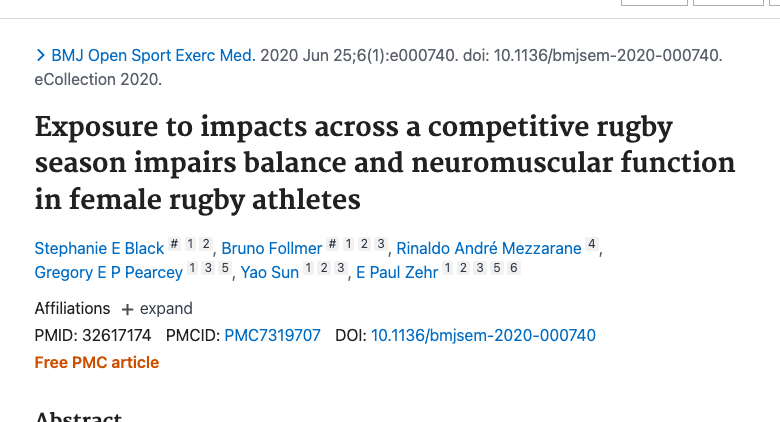

女子ラグビー選手の静的バランス機能や動的バランス機能をシーズン前後でチェックしています。脳振盪を受傷した選手を対象にしたわけではありませんが、興味深かったのでここで合わせて載せてあります

この研究によるとシーズン後の検査では両足バランスとタンデムスタンスでのバランスの低下が見られたとしています。ただし動的バランス機能のスコアは改善したと報告しています

以上、3つの論文を簡単に見てみました!

これらの研究だけで何かが言えるわけではありませんが、以下の様なことが考えられるかもしれません
- 脳振盪後にはNeuromuscular Control(バランス能力や着地時の安定性)などに競技復帰後にも機能低下が残存している可能性
- 参照資料①によれば、片足スクワットよりも片足での着地動作がより違いがあったことから、いわゆる「速い収縮」だったり、瞬発的な力を発揮する際の機能が低下していることも考えられる
脳振盪後にNeuromuscular Trainingを実施した研究

ここからは実際の脳振盪から復帰後のNeuromuscular Trainingを実施した研究を見ていきます
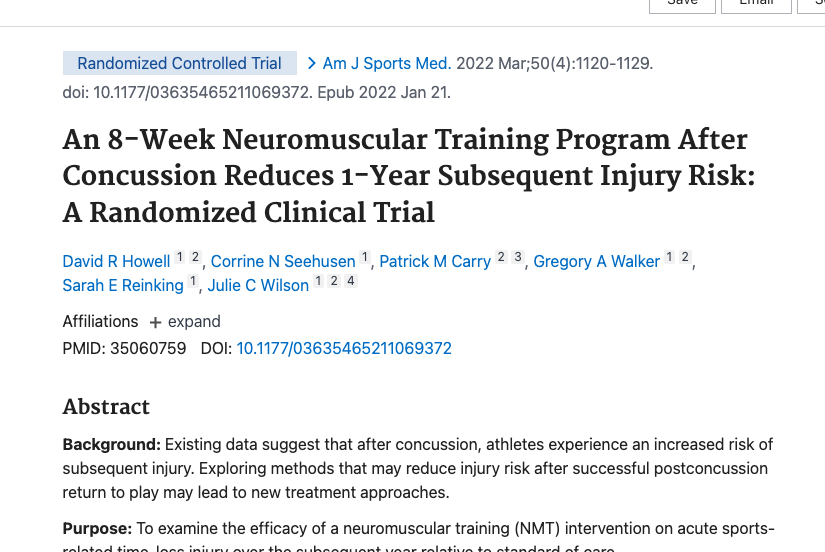

この研究では青少年の脳振盪受傷者を対象に、競技復帰後に8週間のNeuromuscular Trainingを行い、翌シーズンのスポーツ中の怪我の発生率を見た研究です

結果としては脳振盪受傷者で競技復帰後に8週間のNeuromuscular trainingをした群の方が、脳振盪も受傷せずNeuromuscular trainingもやらなかった群よりも怪我の発生リスクは低かったと報告しています

まだこの研究だけでは確かなことは言えませんが、脳振盪から競技復帰した後にNeuromuscular Triainingを行うことで何かしらの悪影響があるとは考えにくいので、それらを取り入れること、もしくは検討する価値はあるかと思います
Neuromuscular Trainingを考える

ここからは上記の研究などから自分の考えをまとめていきたいと思います
- 脳振盪から競技復帰後には怪我の発生リスクが上昇している可能性があり、その理由の1つとしてNeuromuscular Controlの機能低下が考えられる
- それゆえに競技復帰後には怪我予防の一環としてNeuromuscular Trainingを取り入れることは検討すべき
- Neuromuscular Trainingは個人的には静的なバランス動作などの他にも、片足ドロップジャンプなどの動的なもの且つ片足の動作も含めるべきと考える
- またアスリートは多少の機能低下でも代償能力が高い為に一見問題なく動作が行えている場合もあるので、なるべく代償動作が出にくいもの、代償をする”逃げ場”がないもの、もしくは複数のタスクを同時に行う様な難易度が高いものもNeuromuscular Trainingに取り入れた方がいい可能性はある
参照資料
解剖学ブログのご案内

このブログの他にも解剖学に特化したブログも行っています

そちらもご覧いただければ幸いです😄



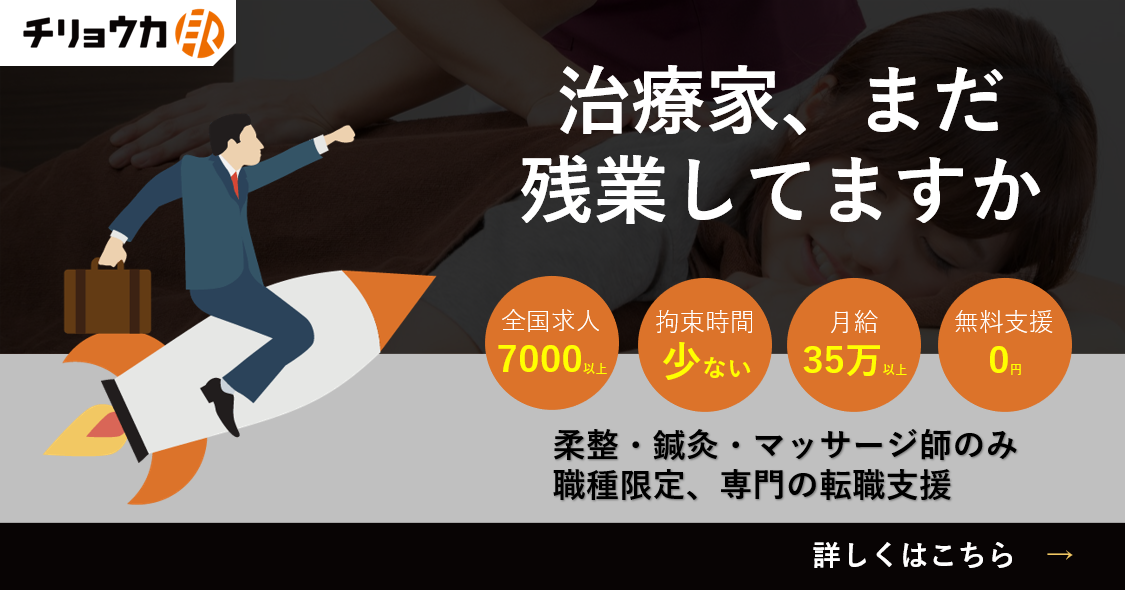




コメント