
こんにちわ、爪川です

脳振盪を一度受傷すると2回目の脳振盪になりやすくなりますが、脳振盪の影響はそれだけでなく下半身を中心にした怪我のリスクも高めると言われています

今回のブログでは「脳振盪からスポーツ復帰後の怪我のリスクの上昇を研究した文献を数本簡単にまとめ、なぜ怪我のリスクが上がるのか」を考えたいと思います

ちなみに以前にNFL(プロアメリカンフットボールリーグ)の選手を対象にした同様の研究に関してブログ記事を書きましたので、そちあらもご覧ください↓
脳振盪から復帰後の怪我のリスクの上昇とその要因の考察
脳振盪からスポーツ復帰後の怪我のリスクの上昇

脳振盪からの復帰後に怪我のリスクが上昇するかどうかを調べた文献は多く発表されています

そのほとんどの文献で脳振盪から復帰後に怪我のリスクは上昇することを示唆しています(参照資料1、2、3、4)
<脳振盪から復帰後、怪我のリスクは上昇する可能性が高い>

これらの文献は高校生、大学生、プロアスリートとさまざまな競技レベルの選手を対象にしているので、どの年代でも当てはまることかと思います

ただ被験者は女性よりも男性の方が多いので、女性に関してはまだ何とも言えない可能性はあります
<高校生、大学生、プロアスリート、どのレベルでも怪我のリスクは上昇すると考えられる>

また、脳振盪を受傷した回数が多ければ多いほど、怪我のリスクも高まる報告をした文献もあります(参照資料1)

ただし、脳振盪からの復帰後、怪我のリスクの上昇は見られなかったと報告している研究もあります(参照資料5)


研究方法や対象によってはこの様に違った結果になる場合もありますが、総じて現在の理解としては「脳振盪からの復帰後は怪我のリスクが上昇する」と言えるのではないかと思います
- 脳振盪から復帰後、怪我のリスク(特に下半身)は上昇する可能性が高い
- 年齢や競技レベルに関わらず、怪我のリスクは上昇すると考えられる
- 女性を対象にした研究は多くなく、男女共に当てはまるかは不明
- 脳振盪を受傷した回数が多ければ多いほど、怪我のリスクが高まる可能性がある
- 脳振盪から復帰後、怪我のリスクに変化はなかったという報告もある
怪我のリスクの上昇に繋がる要因の考察:着地時の変化

脳振盪からの復帰後に怪我のリスクは高まることが示唆されますが、ではなぜリスクが高まるのでしょうか?

ここでは1つの研究を基に考えたいと思います
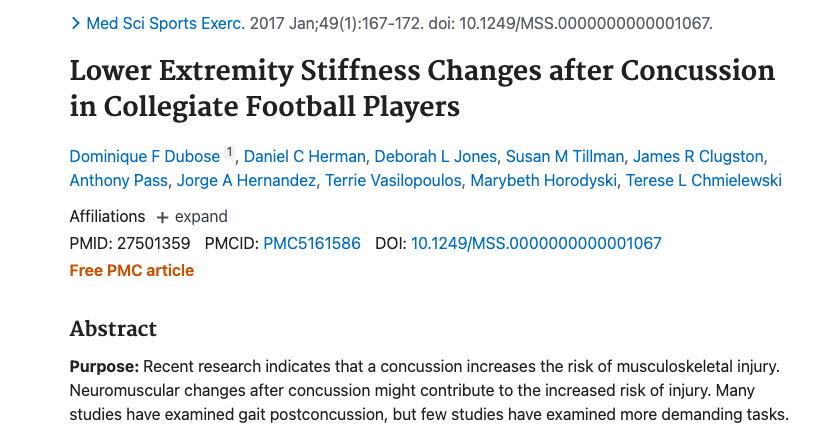

この研究ではアメリカの大学アメリカンフットボール選手を対象とした研究で、約25cm(ほぼ階段一段分)の台から飛び降りて片足で着地した時の下肢の動き方などを研究しています

この片足着地のテストをシーズン前とシーズン後に計測します

この研究によれば脳振盪を受傷した選手は、シーズン後の検査では着地時に股関節のstiffnesが上昇し、膝と下肢全体のstiffnessは減少したと報告しています

これはつまり着地時に膝をあまり曲げなくなったと言ったイメージです

着地動作は怪我が起きやすい動きの1つで、特に膝や足首の靭帯などの怪我が起きやすいシュチュエーションではあります

脳振盪はこの様な動作に「変化」をもたらす可能性があり、それも怪我のリスクの上昇につながる可能性があります

どの様にして脳振盪はこのような「変化」を引き起こすのかは不明ですが、考えられることを以下に列挙してみます
- <筋肉の反応速度が遅くなった?>
- 着地時には瞬間的に筋肉に力を入れて着地の衝撃を受け止める必要がありますが、この反応速度が遅くなっている?
- <着地時のタイミング予想と実際の着地のタイミングのずれ?>
- 着地の際には足が地面に着く前に「いつ」足が着くかをあらかじめ無意識に予想しており、身体の準備が出来ている状態で実際に足が地面についていきます。この「いつ」着地するかは目からの情報や今までの経験などである程度予想しているものですが、脳振盪ではさまざまな機能に障害が起こるので、この「いつ」という予測が若干ズレてくる可能性もあるかと思います
- <無意識的に怖がっている?>
- 台から飛び降りるという動きに対して、心理的に”怖い”という感情があることも考えられます

上記に書き出したことは予想に過ぎないのですが、脳振盪後にneuromuscular control(神経筋制御)は変化するという報告は他の文献でも聞くところです

ですので、脳振盪後の怪我予防やリハビリの一環として、着地時の動作チェックや着地時の床半力測定なども取り入れられる可能性はありそうです
まとめ

今回のまとめです!
- 現在の研究では、脳振盪復帰後に怪我のリスクは上昇すると考えられる
- なぜ怪我のリスクが上昇するかは不明
- ただ、脳振盪後に下肢の着地動作などの変化があり、それらの神経筋制御と関わっていることも考えられる
参照資料
解剖学ブログのご案内

このブログの他にも解剖学に特化したブログも行っています

そちらもご覧いただければ幸いです😄



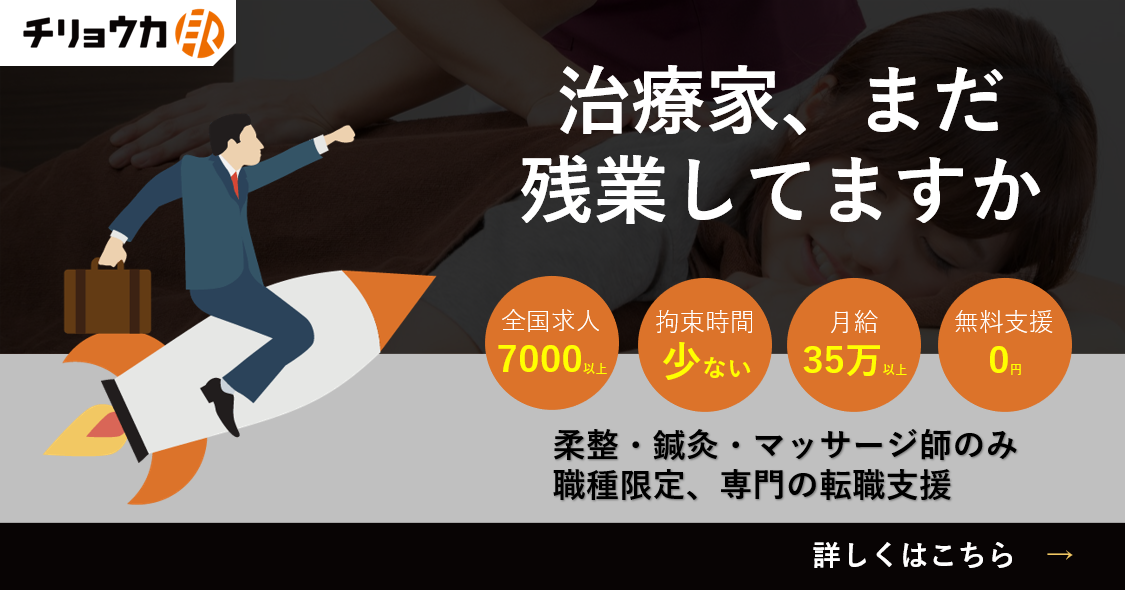



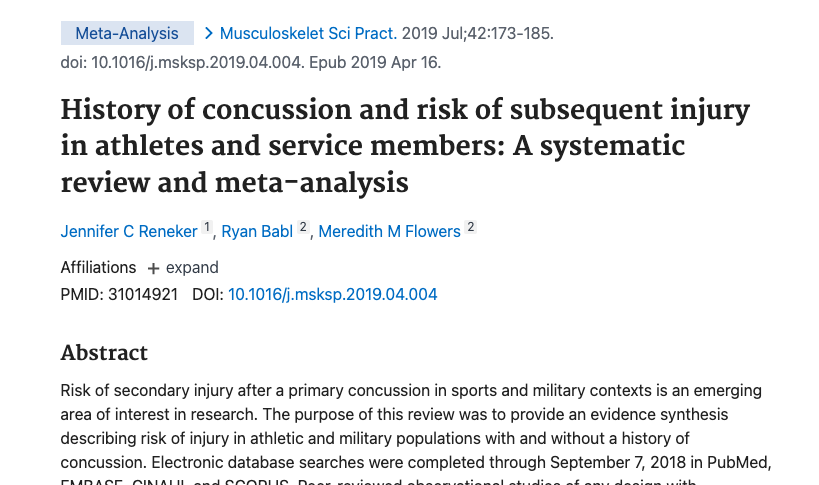
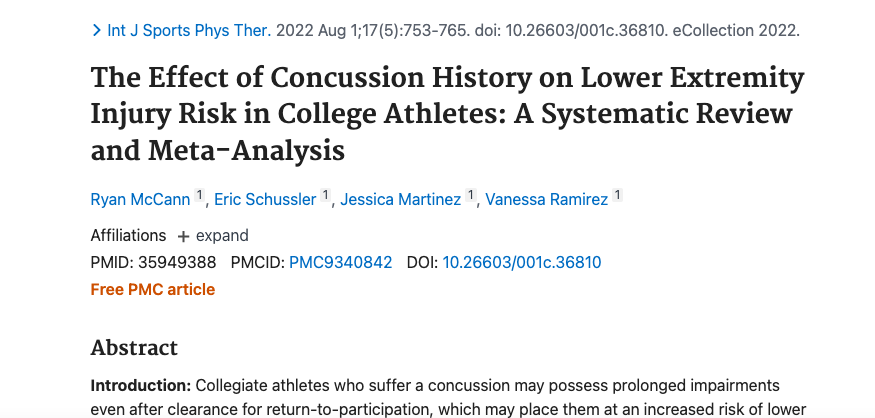
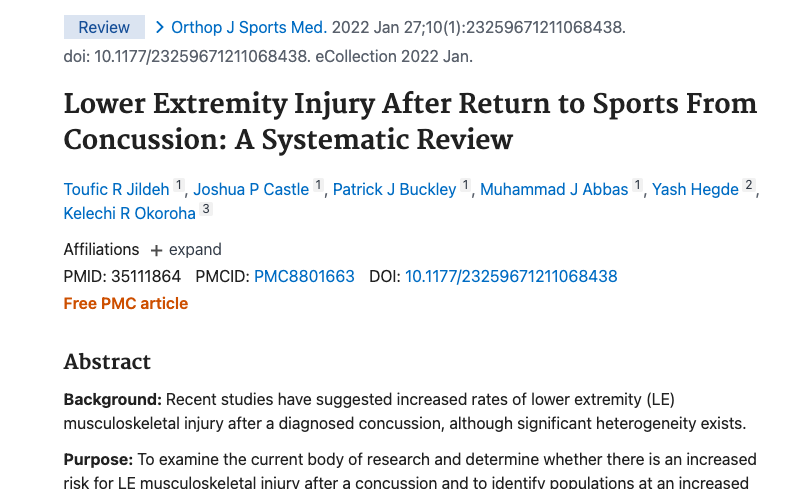


コメント